物価目標「2%」の見直しはなぜ必要なのか ~米国の現実を直視せよ
2022.12.011990年代以降、物価目標政策(インフレ・ターゲティング)を採用する国が増え、2010年代には多くの中央銀行が2%の物価目標を掲げるようになった。「物価目標2%はグローバルスタンダード」と言われる所以(ゆえん)である。
日本銀行も、2013年1月にコア消費者物価の前年比2%を目標とする「物価安定の目標」を導入した。さらに同年4月の異次元緩和では、「(2%を)安定的に持続するために必要な時点まで(これを)継続する」とした。
その後9年半が過ぎたが、今も異次元緩和は続いている。物価目標政策は日本だけがうまく機能していないかのように言われるが、そうではない。最近の世界的な物価高騰は、同政策が海外でも期待したようには機能していないことの表れである。
良好な経済パフォーマンスと整合しない米国物価の2%超え
米国FRB(連邦準備制度理事会)は、12年1月、PCE(個人消費支出)デフレーターの前年比2%を「長期的な物価目標(a longer-run goal of inflation)」とする物価目標政策を導入した。また、毎回の政策決定に当たっては、短期的に振れの大きい食品とエネルギーの価格を除く「コアPCEデフレーター」を重視している。
コアPCEデフレーター(前年比、以下同じ)の実績は、高インフレが収束した90年代半ば以降、ほとんどの期間で1%台で推移してきた(参考1)。2%を超えたのは、96年以降の27年間で、①2005~07年と②21~22年の2回、計5年にとどまる。
(参考1)米国コアPCEデフレーターの前年比推移
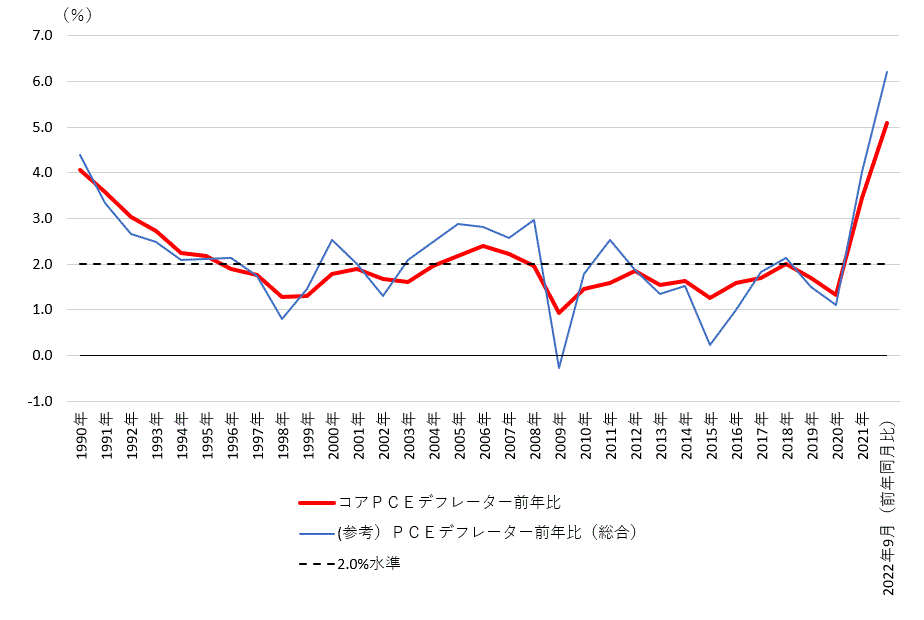
(出典)セントルイス連邦準備銀行「FRED(経済データ集)」を基に筆者作成。
このうち05~07年は、リーマンショック前の経済過熱期に当たる。3年間のコアPCEデフレーターは平均2.3%と、2%をわずかに上回るだけだった。にもかかわらず、金融市場ではバブルが生じ、住宅投資の過熱とその反動からリーマンショックが引き起こされた。
以後、2%を超えたのは今回の物価高騰期だけである。客観的にみれば、コアPCEデフレータの2%超えは、深刻なリスクと表裏一体の関係にある。良好な経済パフォーマンスと整合的な米国の物価上昇率は、2%というよりは、1%台半ばだったように見える。
ただし、FRBが掲げる2%はあくまで「長期的な物価目標」だ。1%台が長く続いても許容範囲内とみなされれば、大きな支障にはならなかっただろう。
米国はなぜ失敗したか
事態を変えたのは、20年初めのコロナ感染の拡大だった。失業率が大幅に上昇し、コアPCEデフレーターの前年同月比も、ごく短期間1%をわずかに割り込んだ。巨額の財政支出が行われ、FRBも政策金利を引き下げるとともに、量的緩和政策を復活させた。
さらにFRBは、20年8月、従来の物価目標政策を改め、「平均インフレ目標(flexible form of average inflation targeting)」を導入した。
「一定期間の平均で物価目標の達成を目指す」とする考え方で、2%を下回る物価が一定期間続く場合には、これを補うよう次の期間は2%を緩やかに超えるインフレ率(moderately above 2%)の実現を目指すというものだった。日本銀行が掲げる「オーバーシュート型コミットメント」と、ほぼ同様の趣旨である。
しかし、これが裏目に出た。
コロナ感染が一服した21年春には国内需要は急回復し、供給不足と相まって物価は上昇に転じた。それでも、FRBは物価の上昇を「一時的」とみなし、大規模な金融緩和を続けた。
結局、利上げを開始したのは、22年3月だった(量的緩和の縮小開始は21年11月)。このころにはロシアのウクライナ侵攻もあり、物価の上昇に弾みがついており、40年振りの高さのインフレ率となった。
平均インフレ目標が政策判断を遅らせた
FRBに見通し違いがあったことは確かだろう。しかし、「平均インフレ目標」の導入が政策判断の遅れにつながったことは否めない。分かりやすく、①物価目標が1.5%であったと仮定した場合と、②今回の平均インフレ目標2%の場合を比べてみよう。
仮に物価目標が1.5%であったとすれば、当時の物価動向からみて「平均インフレ目標」の導入はなかっただろう。そうであれば、2020年末以降の物価上昇をいち早く警戒していたはずであり、遅くとも21年夏までにはなんらかの手が打たれていた可能性が高い(参考2参照)。
(参考2)コアPCEデフレーター(季節調整済み)の前月比年率推移
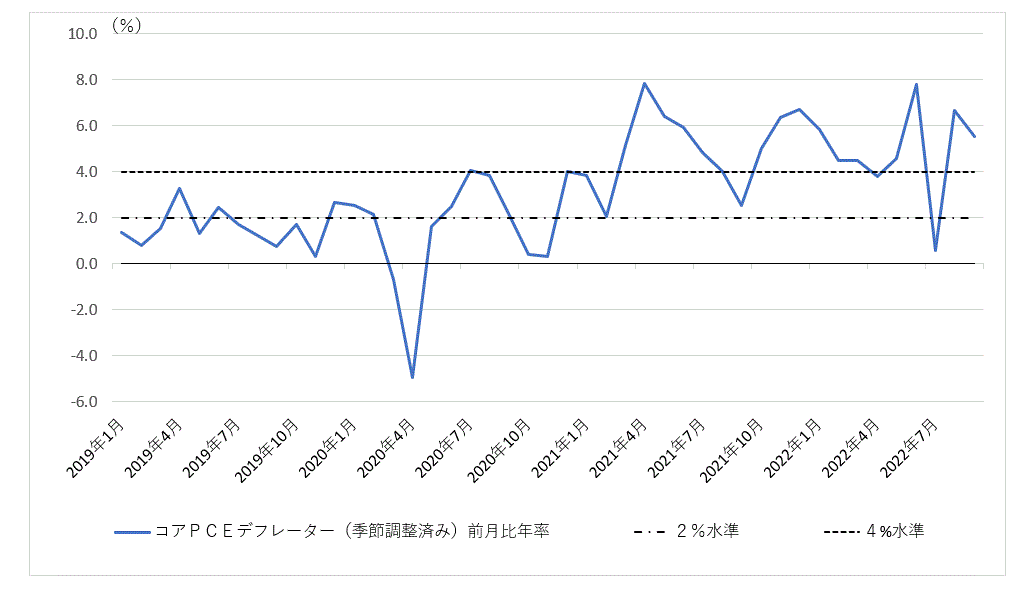
(出典)セントルイス連邦準備銀行「FRED(経済データ集)」を基に筆者作成。
現実は、「平均インフレ目標」の下で、高めの物価上昇を容認する政策運営が行われた。FOMC声明文を見ると、平均インフレ目標導入直後の20年9月会合以降、毎回「2%を下回る物価が長く続いたことを受け、2%を緩やかに超えるインフレ率を目指す」との文言が盛り込まれ、21年11月会合まで続けられた。声明文の中で明確な警戒姿勢が示されたのは、本年に入ってからである。
後知恵ではあるが、政策転換が半年程度遅れた印象にある。平均インフレ目標が政策判断に大きな影響を与えたことは間違いない。
教訓を考える
80年代、ボルカー元FRB議長は政治や世論の反対を押し切って、断固たる引き締め政策をとり、インフレを収束させた。米国内では、これがその後の経済の繁栄をもたらしたと理解されている。40年ぶりの物価高騰に直面するFRBは、何としてでもインフレを収束させなければならないと感じているだろう。
教訓をあげてみよう。
(1)物価目標は国民の物価観の基礎を形成するものであり、中央銀行にとってきわめて重要だ。しかし、「望ましい物価上昇率が奈辺にあるか」はもっぱら実践的な話であり、アプリオリ(先験的)には定まらない。
(2)そもそも、世界一律の「望ましい物価上昇率の水準」があるかどうかは疑わしい。物価統計作成の方法自体も、各国で違う。潜在成長率や失業率などは各国で異なるのが自然であるにもかかわらず、物価にだけは共通のスタンダードがあるとする根拠は、はっきりしない。
(3)「平均インフレ目標」や「オーバーシュート型コミットメント」は、人々の物価見通し(インフレ期待)を長期的に安定させようとする試みだった。しかし、望ましい物価水準自体が不確かである以上、こうした試みで政策を長期的に縛るのはリスクが高い。その時々の経済パフォーマンスと金融政策の効果・副作用に照らして目標値の妥当性を見極め、柔軟な政策運営に努める姿勢が重要である。
(4)金融緩和の副作用は、物価高騰の有無だけではない。典型は資産バブルだが、企業の新陳代謝の遅れや金融システムの弱体化、財政規律の緩みなどにも目を向けなければならない。
(5)ところで、物価目標を「2%」とした根拠の一つには、物価が下振れてもデフレに陥らないよう「(2%分の)バッファーをつくっておく」との考えがあった(いわゆる「のり代」論)。「2%」は、経験に基づく値というよりは、理屈から考えられた値との色彩が濃い。
しかし、本来回避しなければならないのは、ゼロ金利制約と物価下落の間で起きうるデフレスパイラルである。物価指標が前年比マイナスとなるだけで、直ちにデフレスパイラルが起きるわけではない。実際、リーマンショック時も東日本大震災時も、デフレスパイラルは回避されてきた。
にもかかわらず、物価のマイナスが日本経済のすべての元凶とされたのには、多分に政治的な要素があった。おかげで、日本経済にとって最も重要な課題である「生産性の低迷」の問題から目を背けさせられた。
過度のデフレ懸念から物価目標を高めに設定すれば、金融緩和の行き過ぎがもたらされる。過剰な緩和と事後的な修正は、過度の経済の振幅をもたらす。これが過去20年の世界経済の姿ではなかったか。
私たちは、デフレ懸念をどこまで持つべきなのか。どのような情勢をデフレスパイラルの懸念ありと警戒すべきなのか。物価目標を見直す際の欠かせないテーマである。
中央銀行は謙虚さを
中央銀行は、物価目標値を絶対視できるほど、すべてを知っているわけではない。人々のインフレ心理を思いどおりに動かせるほど、心理形成のメカニズムを分かっているわけでもない。
中央銀行は謙虚であるべきだ。
すべてが分かっているわけではないことを前提に、柔軟な政策判断を心掛ける必要がある。物価目標「2%」とその在り方が問われている。
[(参考)前月コラムの続編「地域と付加価値(3/3)」は来月初に掲載の予定です。]
以 上
[関連コラム]
なぜ日銀はここへきて「賃金」を持ち出すのか~繰り返される異次元緩和の「新たな説明」(2022.10.03)
「円安は日本経済にとってプラス」は本当か?(2022.05.06)
異次元緩和の高い自己評価に根拠はあるか(2022.03.01)
国債残高82兆円を「国家財政、破産の危機」と呼んだ時代があった~財政規律はなぜ軽んじられるようになったか(2022.01.04)
