異次元緩和:変質の経緯と再整理 ~金融政策はなぜこうも分かりにくくなったのか
2021.06.01日本銀行の金融政策が、とにかく分かりにくい。根っこにあるのは異次元緩和の変質だ。別次元に変わったといってもよい。それでも日銀は「これまでの政策は適切に機能している」と述べるばかりだ。
中央銀行には、得られた知見や理解を国民や学界に正しく伝える責任がある。今のままでは、説明責任は果たされない。政策が適切かどうかも分からない。
「物価目標へのコミットメント」は能動型から受動型に
異次元緩和の変質を端的に表すのが、物価目標へのコミットメントだ。当初は「2年以内に物価目標2%の達成」を掲げ、「施策の逐次投入はせず、必要な施策をすべて講じる」と言い切った。
しかし、コミットメントは受動型に転換した。本年4月時点の物価見通しは、2023年度でも前年比1%にとどまり、目標に達しない。それでも追加の緩和措置を講じない。「必要な施策をすべて講じる」とした当初の姿勢とは、雲泥の差がある。
「受動型」のコミットメントは、インフレターゲティングの理念からも外れる。インフレターゲティングは、物価目標と見通しのギャップを定期的に計測し、これを埋めるよう政策を調整するのが基本理念だ。今はそうした手法も採らない。
空振りに終わった「期待に働きかける」
変質は、当初の目論見が期待外れに終わった結果である。
異次元緩和が立脚した政策フレームワークは、米国のノーベル経済学者クルーグマン教授らが主張したものに近かった。①中央銀行が物価目標に強くコミットし、②量的拡大の継続を約束すれば、③人々の物価期待(インフレ心理)が高まり、④その結果実質金利が低下し、⑤経済活動が活発になる、というロジックである。これが正しければ、実質金利をマイナスにでき、名目金利ゼロも制約とならない。
物価目標「2年、2%」を掲げ、量的指標「マネタリーベース」を調節目標に据えたのは、まさしくこのロジックに沿うものだった。
しかし、人々の物価期待は一向に高まらなかった。「中央銀行を国民が信じれば、インフレ期待が高まり、実質金利が低下する」との主張は、空振りに終わった。
日銀は、物価目標の達成時期「2年」を放棄した。調節目標も、「量」から「金利」に変えた。政策フレームワークの中核である2つの柱が変質した。受動型コミットメントへの移行は、その延長線上にある。
「2年」の放棄と「2%」への固執
実際、異次元緩和開始後の資金供給はすさまじかった。21年3月までの8年間で、マネタリーベースの増加は+355.4%に達した。しかし、消費者物価指数(全国、総合除く生鮮食品)の上昇は+5.6%(年平均+0.7%)にとどまった。両者の関係は、きわめて希薄である。
物価期待が高まらない理由として、日銀は根強いデフレ心理(適合的期待)を挙げるようになった。しかし、1980年代半ば以降、日本で物価が2%を超えたのは90~92年の3年しかない(消費増税の影響を除く)。しかも、この3年はバブルの後遺症の時期に当たる(参考参照)。
本年4月の日銀見通しに従えば、異次元緩和開始から23年度までの10年間、目標は一度も達成されない。いまさら「適合的期待」を強調されても、物価と実体経済の関係を見誤っていたとしかみえない。「日銀を国民が信用すれば、インフレ期待が高まる」とのロジックは、何だったのか。「物価目標2%はグローバルなスタンダード」との主張も、海外の中央銀行は物価目標に対しもっと柔軟な金融政策運営を行っている。
「2年」は放棄した。調節目標も変えた。それでも、「2%」だけは点検も見直しも行わず、硬直的な政策運営を続ける。それが今の金融政策である。
(参考)消費者物価指数と実質GDPの推移
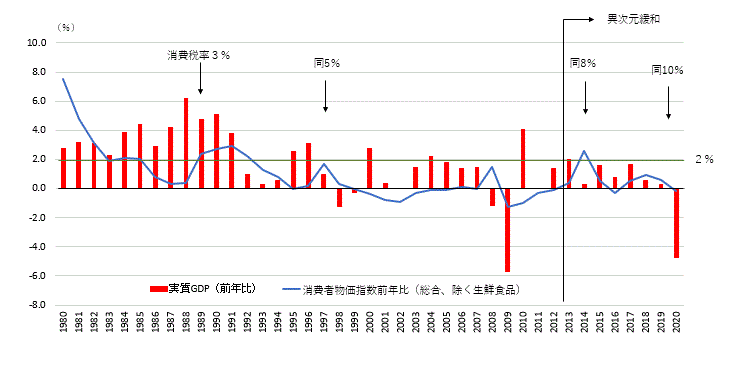
(出典)総務省統計局「消費者物価指数(CPI)」、内閣府「国民経済計算(GDP統計)を基に、筆者が作成。
「量」から「金利」へ、しかし「量」の旗も降ろさない
日銀は金融調節の目標を「量」から「金利」に変えてきた。調節目標が金利であれば、実体経済に及ぼす効果をある程度定量的に推し測ることができる。
しかし、日銀は「量」の旗も降ろさない。16年1月には「マイナス金利政策」の導入にもかかわらず、年間80兆円の国債購入を維持した。この結果金融市場は混乱に陥り、同年9月「イールドカーブ・コントロール」の導入に踏み切ることになった。
そもそも、市場金利の水準と国債購入の金額(マネタリーベースの増加額)を、同時に目標に掲げることはできない。金利目標の達成には資金供給量の伸縮を必要とするからだ。実際、イールドカーブ・コントロールの導入後、日銀は金利誘導を優先するようになり、マネタリーベースの増加額が大きく伸縮するようになった。
しかし、日銀は今も「量」の旗を降ろさない。「オーバーシュート型コミットメント」と称し、「物価が安定的に2%を超えるまでは、マネタリーベースの拡大方針を継続する」としている。
「(マネタリーベースの)拡大」は、単に増加額がプラスでさえあればよいとも解釈できる。従来の「年間80兆円程度」に比べれば、大きな差がある。それでも「金利」と「量」を同時に追い求める表現に、変わりはない。単なるレトリックと受け止めるのが自然だろうが、まともには理解し難い。
アンバランスな効果と副作用の検証
さらに理解を難しくするのは、効果と副作用の検証だ。
物価目標と実績の乖離が続くにもかかわらず、追加の緩和措置は採らない。そうであれば、緩和効果が小さいか、副作用が大きいかのいずれかだろう。
しかし、日銀は、従来の政策が「適切に機能している」と強調するばかりだ。本年3月の「施策の点検」では、効果の検証に多くの定量的分析を行った。「マイナス金利はまだまだ深掘りできる」との説明も行っている。ならば、追加措置を講じない理由は何か。
一方、副作用の方はほとんど分析されない。「施策の点検」でも、定量的と呼べる分析はなかった。
最も警戒すべき副作用は、国債やETFの大量購入が市場機能を低下させ、資源配分をゆがめることだ。金利の超低水準や株価の支持には、成長性の低い企業を温存させるリスクがある。国債の大量購入には、非効率な財政支出をもたらすリスクがある。しかし、これら副作用への言及はなかった。
効果と副作用のバランスのとれた検証と説明がなければ、今の政策を「粘り強く続ける」理由が分からない。あえて解釈すれば、「追加の緩和は、副作用の大きさの割りには効果が小さい」、一方「金利の正常化は、緩和効果を阻害する割りには副作用の軽減効果が小さい」となるか。
しかし、これでは金利引き下げ方向で「緩和効果小、副作用大」を、金利引き上げ方向で「緩和効果大(悪影響大)、副作用小(好影響小)」を想定していることになる。逆方向のベクトルの使い分けは適切か。やはりバランスのある検証が必要だ。
レトリックの積み重ねでコテコテに
異次元緩和は変質した。しかし日銀は、これまでの施策をすべて適切と評価し続けてきた。この見解を維持するために、レトリックと施策が積み重ねられてきたようにもみえる。
第1に、政策委員の間に意見のばらつきがあり、これを包含しようとして、複数の異なるロジックを1つの政策に押し込んできたようにみえる。多数決での意思決定は難しい。しかし、異なるロジックを1つに押し込んでは、政策の首尾一貫性が失われる。
第2に、やはり一種の無謬主義があるのかもしれない。とくに異次元緩和は「中央銀行を国民が信じること」を出発点としていた。国民の信用を維持しようと、完全無欠の姿勢を保っているかのようにみえる。
異次元緩和は今やコテコテの政策である。これで政策を理解せよというのは、無理がある。レトリックを削ぎ落とし、施策を整理して、現時点で依拠するフレームワークをはっきりさせる必要がある。そうすることで初めて、適切な政策かどうかを世に問うことができる。
中央銀行の説明責任は、重い。
以 上
[関連コラム]
日銀の「施策の点検」が「施策の点検」で終われない理由~長期金利の変動幅拡大など(2021.03.01)
日銀のETF買入れ 「リスク・プレミアムに働きかけること」のリスク~株価維持と見られることの危うさ(2020.04.01)
口座維持手数料の論議で語られぬこと~マイナスの預金金利と日銀の説明責任(2019.10.01)
なぜ「構造要因で、6割の地銀が最終赤字に」は曲解なのか~日銀試算が示唆する異次元緩和の深刻な帰結(2019.07.01)
異次元緩和の負のトライアングル~縮む市場経済、軋む金融システム、緩む財政規律(2019.04.26)
