「将来推計人口」が示す日本経済の険しい道のり ~「70代半ばまで働く社会づくりを」再考
2023.06.01先日、国立社会保障・人口問題研究所が新しい「日本の将来推計人口(2023年推計)」を公表した。2020年の国勢調査を基にした推計である。
今回目立つのは、前回の2017年推計(2015年国勢調査)に比べ、外国人の大幅流入超を仮定したことだ。新型コロナ前までの実績をふまえたもので、前回の年約69千人(2035年)から今回は同約164千人(2040年)と、倍増以上を見込んでいる。
その結果、合計特殊出生率の下振れ(前回1.44⇒今回1.36)にもかかわらず、総人口の減少スピードは鈍化している。例えば、2050年時点の総人口(出生中位・死亡中位)は、前回の約102百万人から今回約105百万人へと上振れした(2020年実績:約126百万人)。
外国人のこれほどの流入超を維持できるかは微妙だが、本稿では、今回の将来推計人口(出生中位・死亡中位)を基に、今後の日本経済の課題を確認してみたい。
生産年齢人口は年1%のペースで縮小
参考1は、年齢3区分別の人口推移だ。日本経済にとって最大の課題は、生産年齢人口(15~64歳)の推移が示唆する働き手の減少である。
(参考1)年齢3区分別人口の推移
(出生中位・死亡中位、カッコ内は総人口に占める割合)
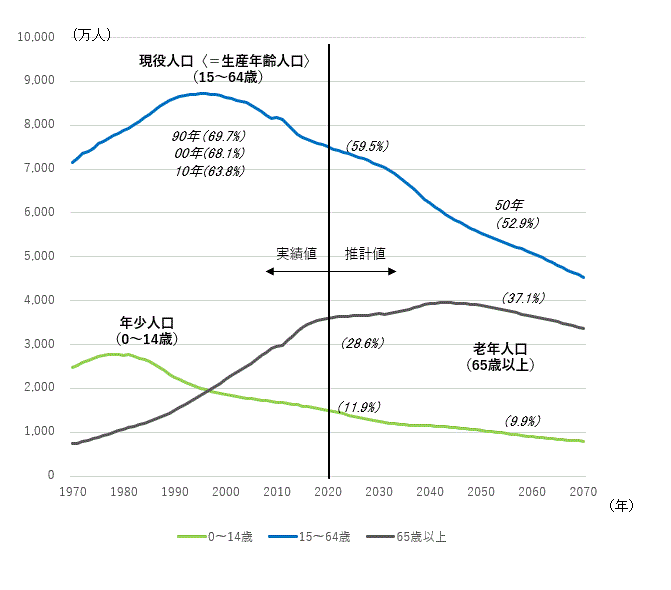
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年推計)」を基に筆者作成。
実質国内総生産(GDP)を供給面からみると、「就業者数」×「労働生産性(就業者1人当たり実質GDP)」で表される。その伸び率である実質経済成長率(実質GDP伸び率)は、「就業者数の伸び」と「労働生産性の伸び」の和にほぼ等しい(後掲参考2参照)。以上の関係を前提に、2050年までの30年間の実質経済成長率を検討してみよう。
簡単化のために生産年齢人口を就業者数の代理変数とすれば、2020年から50年までの就業者数は、年率ー1.01%のスピードで縮小する。1995年から2020年までの25年間(年率ー0.71%)に比べ、縮小ペースは約4割加速する計算となる。
一方、労働生産性の伸びは、先進国の場合、精々年率1%程度との見方が多い。実際、2000~19年のG7諸国を見ると、労働生産性の伸びが年率1%を超えたのは米国(1.3%)だけであり、英国、フランス、ドイツ、カナダ0.6~0.8%、日本0.5%、イタリア-0.4%だった(世界銀行の統計による)。
以上をふまえると、「就業者数の伸び」と「労働生産性の伸び」の和にほぼ等しい実質経済成長率は、次第にプラスの維持が微妙となってくる。とくに生産年齢人口の縮小ペースが速まる2030年以降は、マイナス成長となる年が増えてもおかしくない。
「国民1人当たり実質GDPの伸び率」の維持も容易でない
ただし、実質経済成長率のマイナスを過度に悲観視する必要はない。生産年齢人口がこれほど急速に減る社会にあっても、経済規模だけは従来と同じ水準を維持しようとすること自体が、そもそも無理のある話とも言える。
むしろ大事なのは、実質GDPを総人口で割った「国民1人当たり実質GDPの伸び率」の維持である。1年間に生み出した付加価値を、国民一人ひとりにどれほど割り当てられるかをみる指標だ。この方が、実質GDP伸び率よりも「国民の豊かさ」により近い指標といえる。
しかし、この「国民一人当たりの実質GDPの伸び率」を維持するのも、容易でない。なぜなら、2050年ごろまでは生産年齢人口の減少スピードが総人口の減少を上回り続けるからだ。
生産年齢人口の減少は2030年代に加速する一方で、老年人口は2040年代半ば以降緩やかに減少する。その結果、総人口に占める生産年齢人口の割合は低下を続ける。すなわち、1年間に生み出された付加価値を、より多くの国民で分け合わねばならない計算となる(注)。
(注)総人口に占める生産年齢人口の割合は、1990年約70%、2000年約68%、20年約60%だったものが、50年には約53%まで低下する。大づかみにいえば、就業者2人で生み出した付加価値を2000年は約3人で分けていたが、50年には約4人で分け合わなければならない計算である。
以上を式で表すと、「国民1人当たりの実質GDPの伸び率」は、「就業者数の伸び」から「総人口の伸び」を差し引き、「労働生産性の伸び」を加えたもので近似される。このうち、前2者の2050年までの30年間の値は、年率ー0.39%となる。このハンディキャップを労働生産性の向上でカバーしない限り、「国民1人当たりの実質GDPの伸び率」は低下することになる(参考2参照)。
(参考2)実質GDPおよび国民1人当たり実質GDPの伸び率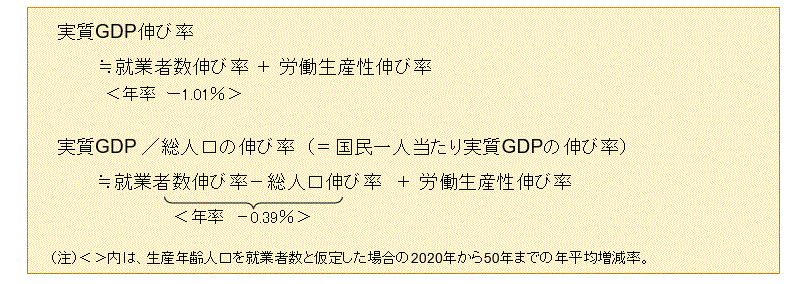 (注)カッコ内の数値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年推計)」を基に筆者試算。
(注)カッコ内の数値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年推計)」を基に筆者試算。
(出典)筆者作成。
高齢層の就業者を増やしてハンディキャップを打ち返す
上記のハンディキャップ(年率ー0.39%)を打ち返すには、①就業者を増やすか、②労働生産性の伸びを高めるしかない。このうち労働生産性の向上はきわめて重要な課題だが、過度の期待をもつことも禁物だろう。デジタル化など、これまで多額の予算を投入したものの、目に見えた成果は得られていない。
より確実な方策は、就業者を増やすことである。期待は外国人の流入超拡大だが、すでに述べたように、今回の「将来推計人口」自体が大量の流入超を前提としており、これ以上を望むのは難しい。
そうであれば、現役人口の拡大、すなわち高齢層をできる限り労働市場に維持することである。上記の試算の世界でいえば、「生産年齢人口」の定義を変更し、上限年齢を引き上げることで潜在的な労働力を増やすことだ。
前記注のとおり、2050年時点の総人口に占める生産年齢人口の割合は約53%となる。これを、2000年実績(約68%)並みに引き戻す計算をすると、生産年齢人口の定義を15~64歳から15~75歳に変えればよいとの結果となる。
必ずしも荒唐無稽な話ではない。日本経済がこうした課題を抱えることになった理由の一つは、長寿化である。長寿化は日本の医療、介護の充実の結果であり、喜ばしいことだが、背後では誰かがコストを負担しなければならない。
長寿で引退後の年数が伸びているにもかかわらず、もし従来の平均勤労年数を維持すれば、若者たちの負担が増す理屈となる。若者世代が、負担を懸念してますます子供をもたなくなれば、本当の悪循環だ。
長寿の恩恵を享受するには、長く働くしかない。政府は企業に対し70歳までの雇用努力を義務づけたが、これでは到底間に合わない。子や孫の世代に豊かな社会を引き継ぐには、「70代半ばまで働く社会づくり」を急がなければならない。
以 上
[関連コラム]
「少子化対策の財源は高齢世代の負担を中心に~出生率に及ぼす効果に配慮を」(2023.05.08)
シリーズ「人口動態と労働市場」(全5回)(2021.07.01~2021.11.01)
シリーズ「人口構成と日本経済」(全5回)(2021.04.01~2021.0616)
「なぜ私たちは70歳代まで働かねばならないのか~社会生活から考える日本経済」(2015.01.05)
「70歳まで働いて帳尻を合わせよう~長寿高齢化社会の道理を考える」(2013.09.02)
